『消費者向けデバイスのNothing、英国最新のユニコーンに』、『CuspAI、材料向けAI検索エンジンでアジア大手投資家から資金調達』、『AI自律型研究ラボを展開するLila Sciences、2億3,500万ドルを調達』、『クシュナー氏が新AIスタートアップ立ち上げ、企業の生成AI活用を支援』、『独X-FAB、サラワク州半導体工場に30億リンギを追加投資』、『Lego、ベトナム南部に5番目の地域配送センターを開設』、『Samsung、AIなど主要技術分野で学術機関との連携強化』、『グリーンテックとモビリティに焦点、産学間で新覚書締結』を取り上げた「イノベーションインサイト:第151回」をお届けします。

ロンドンを拠点とする家電スタートアップのNothingは、Tiger Globalが主導し、Google VenturesやQualcomm Venturesなども参加したシリーズCラウンドで2億ドルを確保した。これにより、累計調達資金は4億5,000万ドル、企業価値も13億ドルに達し、英国の最新ユニコーンとなった。2020年設立のNothingは、スマートフォン、スマートウォッチ、ヘッドホンの開発で、家電市場に革新をもたらすことを目指している。差別化を図るためデザインに大きく依存してきた同社だが、その透明感のある美学と特徴的なユーザーインターフェースが、同ブランドに独自のアイデンティティを確立させる一助となっている。同社によると、創業以来、これまでに510万台のデバイスを出荷し、売上高10億ドルを達成したという。なお、今回の調達資金は、高度なパーソナライズ化機能と文脈理解能力、さらに適応性を備えたAIオペレーティング・システムの構築に充てられる予定で、2026年に同社初AとなるIネイティブのデバイスを発売する。

ケンブリッジを拠点に生成AIを活用した材料探索技術を開発するCuspAIが、1億ドルのシリーズA資金を調達した。同ラウンドにはNVIDIAのベンチャーキャピタル部門であるNVentures、Temasek、Samsung Ventures、Hyundai Motor Groupなどが参加した。今回の資金調達は、同社が3,000万ドルを調達したシードラウンドからたった1年しか経っていない中での実施となった。2024年に設立されたCuspAIは、材料向けのAI「検索エンジン」として機能するプラットフォームを開発している。これにより利用者は必要な特性を正確に指定し、従来の探索手法に比べて最大10倍の速度で合成可能な新規候補物質を生成できるという。この技術は材料に依存しないことから、自動車、半導体、エネルギー、気候変動など複数の産業に影響を与える可能性を秘めている。同社は既に現代自動車と持続可能なエネルギー分野で提携を結んでいるほか、化学メーカーのKemiraとPFAS除去技術、Metaとも直接空気回収技術で協業中だという。CuspAIは、この調達資金をプラットフォームの拡張に充て、材料の市場投入を加速させる方針だ。

AIを活用した自律型研究ラボ「AI Science Factories」の開発を進めるLila Sciencesは、シリーズAラウンドで2億3,500万ドルを調達した。今回の資金調達により、同社の累計調達額は4億3,500万ドルに到達。ラウンドはBraidwellとCollective Globalが主導し、Altitude Life Science Venturesやアブダビ投資庁傘下ファンドなどが参加した。2023年に設立されたLilaは、Flagshipパートナーのジェフリー・フォン・マルツァーン博士がCEOを務め、遺伝子工学の第一人者ジョージ・チャーチ博士がチーフサイエンティストを担う。LilaはAIを基盤に科学的仮説の生成から実験設計・実行・分析・反復までを自動化し、科学研究における「超知能」の実現を目指す。今回の資金により、ボストン、サンフランシスコ、ロンドンの拠点を拡充し、AI・独自ソフトウェア・カスタムハードウェアを統合した“科学的方法マシン”の開発を加速。既に生命科学、化学、マテリアル分野で数千件に及ぶ発見を実現しており、科学オートメーションの新時代を切り拓こうとしている。

米大統領トランプ氏の義理の息子であるジャレッド・クシュナー氏が、投資家のエラッド・ギル氏、元メキシコ外相のルイス・ビデガライ氏とともに、AIスタートアップBrain Co.をサンフランシスコに設立。シリーズAで3,000万ドルを調達した。ラウンドはクシュナー氏のAffinity PartnersとGil Capitalが主導し、Coinbaseのブライアン・アームストロング氏やLinkedIn共同創業者のリード・ホフマン氏など著名なエンジェル投資家が参加した。2024年創業の同社はOpenAIと戦略提携を結び、Sotheby’sやWarburg PincusをはじめとするFortune Global 2000の10社以上の企業にサービスを提供。エネルギー、ヘルスケア、ホスピタリティなど多様な業界で、GPT-5などの基盤モデルと実業務の橋渡しとなる業界非依存のAIアプリケーションを展開している。ホテル予約からエネルギー最適化まで、具体的なユースケースに対応。Serene AIの買収を通じてプロダクト強化も進めており、Google BrainやDatabricks、Clubhouse出身の人材を経営陣に迎えている。クシュナー氏とギル氏は、Brain Co.を「優れたAI人材と世界の企業・行政機関をつなぐプラットフォーム」と位置づけ、AI導入の大衆化と業務変革を後押しする構えだ。

ドイツの半導体メーカーX-FABは、マレーシア・サラワク州の工場に30億リンギを投資し、月間生産能力を3万枚から4万枚へ拡大すると発表した。今回の投資は、自動車・医療・産業分野向け先端半導体を対象としており、マレーシアが世界的な半導体サプライチェーンにおいて果たす役割をさらに強化する狙いである。マレーシア投資・貿易・産業大臣テングク・ザフルル氏は、この拡張が同国の長期的な産業戦略に対する国際的な信頼を示すものであり、先進製造拠点としての地位を高めると述べた。MIDA(マレーシア投資開発庁)は、当該プロジェクトが高付加価値雇用の創出、技能開発、現地サプライチェーン強化を通じ、社会経済的利益を促進すると強調した。新たな製造ラインにより、X-FABの180nm BCD-on-SOI技術の生産能力は倍増する。既に稼働を開始しており、世界顧客への安定供給を担うとともに、マレーシアが掲げる「先端技術を基盤とした高所得工業国」という国家的ビジョンの実現を後押しする。
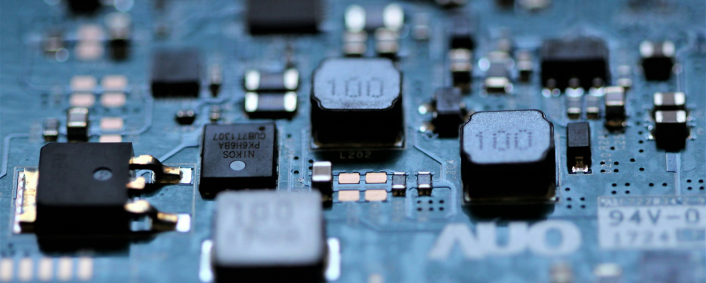
デンマークの玩具メーカーであるLegoは物流大手 Kuehne+Nagelとの提携を拡大し、ベトナム・ドンナイ省に5番目のグローバル地域配送センターを開設した。ジャンディエン工業団地に位置する施設は延床面積1万200平方メートルを有し、アジア太平洋地域では上海に次ぐ2番目のRDCとなる。2026年の完全稼働時には週150本以上のコンテナ処理と最大3万3,000パレットの保管が可能となる見込みである。同センターはホーチミン工場から出荷される製品を、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールおよび日本市場に供給し、来年にはインドとインドネシアへの展開も予定している。物流業務はクネー・アンド・ネーゲルが統括し、輸送、通関、倉庫管理、地域配送を担う。Lego社は、この新拠点がアジアにおける長期的成長を支える俊敏なサプライチェーン構築に寄与すると述べた。また Kuehne+Nagelは、レゴのグローバルな持続可能性目標に沿い、ラストマイル配送において持続可能な船舶燃料や電気自動車を導入する方針を示した。
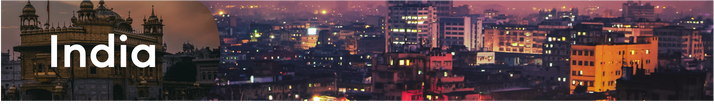
Samsungは現在インドにおいて、若者を対象としたイノベーションと社会貢献のための問題解決を促進する広範なCSR戦略の一環として実施しているInnovation Campus(SIC)プログラムを拡大し、2025年に2万人(前年比で約6倍)の学生を10州にまたいで育成することを目指している。これらの取り組みは、教育へのアクセス向上、創造性の育成、そして技術主導の未来で繁栄するインドの次世代人材の育成を目的に、AI、IoT、ビッグデータ、コーディング・プログラミングなどの分野に焦点を当てている。同社はこの実現に向け、国家技能評議会であるインド電子産業技能評議会(ESSCI)と通信産業技能評議会(TSSC)、それぞれと覚書を締結した。なお、Samsungはウッタル・プラデーシュ州とタミル・ナードゥ州でそれぞれ5,000名の学生を訓練する計画で、都市部と準都市部の双方に支援を提供することで、次世代技術スキル普及を民主化することを目指している。

パンジャブ大学のアクセラレーターであるPI-RAHIとインド工科大学ロパール校が、持続可能なモビリティとグリーンエネルギー技術に関する協業に向け、Hyundai Mobisの子会社で、自動運転やスマートモビリティなどの先進的な自動車技術を専門とするHL KLEMOVE India Pvt と覚書を締結した。この提携は、電気自動車、省エネルギーシステム、車両接続性、先進運転支援システム(ADAS)などの主要分野における共同研究、技術移転、学生インターンシップ、パイロットプロジェクトの推進を目的としている。今後学術研究能力と産業の専門知識を組み合わせることで、インドで力強い成長を見せるスマート交通分野に向けた実用的で拡張性のあるソリューションの開発を目指している。また、イノベーションによる環境負荷低減と産学連携強化に向けた幅広い取り組みを反映しており、クリーンで知的な交通システムの開発に貢献し、グリーンテック分野における将来の人材育成を後押しすることが期待されている。